磁器で涼し気に
先日のテレビの影響でお客さんわんさか!
なんてことは全くなく、放送後すぐにお休みに入ってしまいましたし特に反響はありません♪
あ、でも番組をご覧になった男性に
「風間トオルさんと阿部寛さんは自分の世代のツートップですから」
とご来店いただいたのが嬉しかったです。
僕の世代のモデルだと誰だろう…ちょい上だけど村上淳さんとかARATAさんとかだったかな!?
そして遅くなってしまいましたが、先週は休業いただきありがとうございました!
沖縄入りと同時に梅雨入りして毎日雨が降ったり止んだりでしたが、おかげさまでやちむんと琉球ガラスの仕入も無事にでき既に先着の半分ほどは店頭に並んでいます。
息子が生まれてからは初の渡嘉敷島では親子で自然を満喫してきましたよ。
さて、お休み直前直後で阿部さん八田さん、北窯宮城工房にガラス工房清天と毎日のように入荷が。
全然ブログが追っついてませんが順に紹介していきますね。
まずは5月にしては異様に暑かったところに届いた阿部春弥さんの磁器。
阿部さんの磁器は繊細な仕事ながら割りと厚手で丈夫です。
レンジやラップをしての保存にも気を遣わなくていいですし、日常でガシガシ使いたいですね。
 白磁面取コーヒーカップ(W10.8xD8xH7.4cm/¥3,024/阿部春弥)
白磁面取コーヒーカップ(W10.8xD8xH7.4cm/¥3,024/阿部春弥)
丁寧に面取られ端正な形をしたコーヒーカップは標準的なサイズで容量150mlほど。
少し釉の流れや溜まりもあって味があり、青みを帯びた白磁に珈琲が映えそうです。
自分もですが夏でも珈琲はホット派な貴方、カップを涼し気なものにするだけで違いますよ。
 白磁陽刻唐草文5寸皿(Φ15.2xH2.5cm/¥2,592/阿部春弥)
白磁陽刻唐草文5寸皿(Φ15.2xH2.5cm/¥2,592/阿部春弥)
薄っすらと凸状に浮かび上がった唐草文が華やかで上品な5寸皿です。
フラットな形がお茶請けのケーキも綺麗に置け、おはぎなど和菓子でもイイ感じ。
取皿としても適当なサイズですし、1人分のお刺身やハレの日の1品にも良さそうです。
 白磁鎬 リム小鉢(Φ15.5xH4cm/¥2,160)、6寸深皿(Φ17.5xH4.5cm/¥2,376) ともに阿部春弥
白磁鎬 リム小鉢(Φ15.5xH4cm/¥2,160)、6寸深皿(Φ17.5xH4.5cm/¥2,376) ともに阿部春弥
らせん階段状のちょっと変わった鎬がリムに入れられた器が2種。
細かな鉄粉や色合いが優しく、すっきり過ぎず五月蝿過ぎず料理や場面を選びません。
リム小鉢は中央にボリュームを出して盛れば大きめのリムが余白となり盛り映えします。
お浸しや冷奴もいいですし、5寸ちょっとと取皿や取鉢としても使いやすいサイズです。
6寸深皿は広めの見込みに縁が立ち上がった使い勝手のいいサイズと形。
家族のお惣菜に、また銘々の汁気ある煮魚や揚げ物に(染みの心配なし)、大きめの取皿にも◎
 白磁7寸片口鉢(W21.5xD21xH5.5cm/¥4,536/阿部春弥)
白磁7寸片口鉢(W21.5xD21xH5.5cm/¥4,536/阿部春弥)
広い見込みに平べったい形が特徴的な片口鉢。
白磁の大きなものはのっぺりしがちですが、縁のロクロ目や片口がアクセントになっています。
食卓中央の盛鉢として活躍するサイズで、装飾的な片口ですが手羽大根などの煮汁も注げます。
 ルリ輪花小鉢(Φ12.5xH5.8cm/¥2,160/阿部春弥)
ルリ輪花小鉢(Φ12.5xH5.8cm/¥2,160/阿部春弥)
艶やかで深い瑠璃色が繊細な稜花の縁と相まって凛とした佇まいの小鉢。
淡くなったエッジのブルーも綺麗で、丸みのある形からシャープ過ぎることもありません。
濃色の器は食材の色が映えますし、苺やプチトマトなんかを入れるだけでも可愛いです。
 同小鉢にひろうすの煮物
同小鉢にひろうすの煮物
白磁で涼しげに
梅雨明け前なのに毎日30℃を超える暑さに熱帯夜。
急に来た本格的な暑さに身体がついていきません。
息子は保育園で水遊びやプールを毎日楽しんでいるようで羨ましいです。
泥んこやびしょびしょの洗濯物となり戻ってくる息子のパンツは生意気にも柄物のボクサータイプ。
3歳児のくせに…。
自分のころは小学生までは恐らくクラス全員白ブリーフだったんですけどねぇ。
中高生になり色物のブリーフやトランクスを履いたときは大人の階段を上った気がしたものです。
といっても今は子ども用の売場でも大半が色付きか柄物で、白ブリーフの方が珍しいみたいです。
確かに汚れが目立つ白だと泥んこ汚れとか洗濯が大変ですし理には適っているかと。
でも純粋無垢な子どもには清潔感溢れる純白のブリーフを履いてもらいたいなぁ。
暑い夏に合わせたように磁器続きの入荷です。
今度は長野の阿部春弥さんから白磁のうつわが届いています。
純白ブリーフとは違いやや青みを帯びた色合いが涼しげです。
ツルッと淡白になりがちな白磁ですが、鎬や陽刻など装飾が施され味わいあるものとなっています。
また阿部さんの白磁は割りと厚手で作りがしっかりしているのも特徴です。
 白磁しのぎチューリップマグ(W11xD7.7xH8.7cm/¥3,456/阿部春弥)
白磁しのぎチューリップマグ(W11xD7.7xH8.7cm/¥3,456/阿部春弥)
その名の通りチューリップのような形に小気味よく鎬の入ったマグです。
緩やかなラインのカーブが美しく、端正ながらも手仕事らしさの残る柔らかな鎬もイイ感じ。
ガッシリとした作りの磁器で8分目容量170ml。
自宅でも職場でも珈琲その他何かと使いやすいサイズだと思います。
 白磁端反飯碗(Φ11.6xH5.7cm/¥2,376)、白磁しのぎ飯碗(Φ11.3xH6cm/¥3,024) ともに阿部春弥
白磁端反飯碗(Φ11.6xH5.7cm/¥2,376)、白磁しのぎ飯碗(Φ11.3xH6cm/¥3,024) ともに阿部春弥
白磁のご飯茶碗が2種、どちらも標準的なサイズです。
左の端反りのものは僅かに外に反り返った口縁が口当たりよく、下に入れられた段のラインがアクセントになっています。
やや高めに作られた高台などシンプルながら味があります。
一方右のしのぎ飯碗は太めの鎬とやや深さのある形が特徴的。
ご飯茶碗ではありますが、小鉢に使っても良さそうですし中華スープなんかもいいかもしれません。
 白磁陽刻三島文6寸深皿(Φ18xH4.4cm/¥2,808/阿部春弥)
白磁陽刻三島文6寸深皿(Φ18xH4.4cm/¥2,808/阿部春弥)
土ものの装飾技法である三島手の文様を白磁に陽刻で表現したシリーズの新作です。
遠目には無地にも見えそうな具合にほんのりと浮かんだ感じが上品。
縁が緩やかに立ち上がり深さがある6寸皿。
6寸皿はフラットな平皿かこの形が使いやすくて個人的に好きです。
1人分のおかず、汁気のある煮魚、冬場ならおでんやロールキャベツにって感じですね。
新着いろいろ
本格的に蒸し暑くなる前にと店のエアコンフィルターを掃除しました。
既に日中弱く入れている冷房の効きが全然違います。
最近の家庭用はお掃除不要のものもあり楽になりましたね。
店に備え付けのエアコンはかなり年季が入っており、型番から調べてみたら25〜6年前のもの。
それを掃除した掃除機は自分が一人暮らしを始めたときに購入したスティックタイプで18年目。
なかなかの組み合わせです。
どちらも特にトラブルなく現役ですし、最近の家電に比べ昔のものは丈夫な印象。
機械的にシンプルだから!?ですかね。
さて、実は今月は色々と小さな入荷がありました。
1人の作り手からドーンという通常と違い、お客様からのまとまった注文と合わせてとか、注文していた器のうち先に出来上がった分、また遅れていた分をとか届けていただくことがあります。
ちょっとまとめてご紹介。
 灰粉引兜鉢(Φ12.8xH4.7cm/¥2,376)、灰粉引リム鎬7寸皿(Φ21.5xH3.2cm/¥4,536)
灰粉引兜鉢(Φ12.8xH4.7cm/¥2,376)、灰粉引リム鎬7寸皿(Φ21.5xH3.2cm/¥4,536)
ともに叶谷真一郎
神戸の叶谷真一郎さんの灰粉引が先月のマグ、めし碗、5寸リム皿に追加で届いています。
浮き出た鉄粉や縮れた白化粧が土っぽくも、端正な形にしっとりした質感からどこか品があります。
兜(甲)鉢は鎧の兜を裏返したような形状で、リムと深さからバランスよく盛りつけしやすい鉢です。
お浸しやきんぴらごぼうみたいなお惣菜もグッとよく見えますよ。
リム鎬7寸皿は広くフラットな見込みに立ち上がったリムのカーブや鎬がキレイです。
こちらはメインのおかずからカレー、パスタにといった感じに多用途に活躍してくれます。
 盆栽文八角長皿(W18.2xD11.5xH3cm/¥3,456/稲村真耶)
盆栽文八角長皿(W18.2xD11.5xH3cm/¥3,456/稲村真耶)
こちらはお客さまからの注文分と合わせてたくさん作っていただき再入荷しました。
やや青みを帯びた白磁の色合いに少し滲ませて描かれた盆栽の染付けが愛らしいです。
古物のような雰囲気のなかにどこかとぼけた感じもあり稲村さんらしい器だと思います。
1人分のお造りなんてバッチリですが、出汁巻き卵やエノキベーコン的な居酒屋メニューも◎
 白磁輪花楕円鉢(W17.5xD16.5xH5cm/¥3,240/阿部春弥)
白磁輪花楕円鉢(W17.5xD16.5xH5cm/¥3,240/阿部春弥)
阿部春弥さんから白磁の器が届いています。
縁が花弁状になった輪花の鉢ですが、ゆるめの楕円になっています。
色合いや形が特徴的で食卓でアクセントになりそうです。
楕円の形から正面が決まり盛りつけしやすいのもポイント。
使い勝手のいい5.5寸の鉢のようなサイズ感で、大根と小松菜の煮物とかが合いそうです。
 白磁鎬矢羽根 4寸甲鉢(Φ12xH4.5cm/¥1,512)、5.5寸甲鉢(Φ16.8xH6.3cm/¥3,456)
白磁鎬矢羽根 4寸甲鉢(Φ12xH4.5cm/¥1,512)、5.5寸甲鉢(Φ16.8xH6.3cm/¥3,456)
ともに阿部春弥
前回好評だった甲鉢が両サイズそろって再入荷しました。
同じようなサイズの甲(兜)鉢でも叶谷さんの灰粉引とはまた印象が違いますね。
リムに入れられた矢羽根模様の鎬には釉の濃淡が出ていてウットリ。
ちょっとした惣菜の小鉢に使い勝手が良さそうな4寸は青菜のお浸しなんて綺麗だと思います。
5.5寸は煮物やサラダ、つみれ汁みたいな汁物もいいと思います。
 同5.5寸甲鉢に白菜とツナの炊いたん。あまりものの手抜き料理ですが美味しいですよ。
同5.5寸甲鉢に白菜とツナの炊いたん。あまりものの手抜き料理ですが美味しいですよ。
 白磁面取コーヒーカップ(W10.8xD8xH7.4cm/¥3,024/阿部春弥)
白磁面取コーヒーカップ(W10.8xD8xH7.4cm/¥3,024/阿部春弥) 白磁陽刻唐草文5寸皿(Φ15.2xH2.5cm/¥2,592/阿部春弥)
白磁陽刻唐草文5寸皿(Φ15.2xH2.5cm/¥2,592/阿部春弥) 白磁鎬 リム小鉢(Φ15.5xH4cm/¥2,160)、6寸深皿(Φ17.5xH4.5cm/¥2,376) ともに阿部春弥
白磁鎬 リム小鉢(Φ15.5xH4cm/¥2,160)、6寸深皿(Φ17.5xH4.5cm/¥2,376) ともに阿部春弥 白磁7寸片口鉢(W21.5xD21xH5.5cm/¥4,536/阿部春弥)
白磁7寸片口鉢(W21.5xD21xH5.5cm/¥4,536/阿部春弥) ルリ輪花小鉢(Φ12.5xH5.8cm/¥2,160/阿部春弥)
ルリ輪花小鉢(Φ12.5xH5.8cm/¥2,160/阿部春弥) 同小鉢にひろうすの煮物
同小鉢にひろうすの煮物

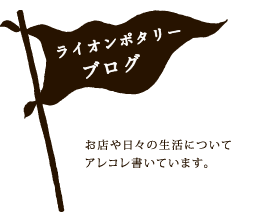
 白磁しのぎチューリップマグ(W11xD7.7xH8.7cm/¥3,456/阿部春弥)
白磁しのぎチューリップマグ(W11xD7.7xH8.7cm/¥3,456/阿部春弥) 白磁端反飯碗(Φ11.6xH5.7cm/¥2,376)、白磁しのぎ飯碗(Φ11.3xH6cm/¥3,024) ともに阿部春弥
白磁端反飯碗(Φ11.6xH5.7cm/¥2,376)、白磁しのぎ飯碗(Φ11.3xH6cm/¥3,024) ともに阿部春弥 白磁陽刻三島文6寸深皿(Φ18xH4.4cm/¥2,808/阿部春弥)
白磁陽刻三島文6寸深皿(Φ18xH4.4cm/¥2,808/阿部春弥) 灰粉引兜鉢(Φ12.8xH4.7cm/¥2,376)、灰粉引リム鎬7寸皿(Φ21.5xH3.2cm/¥4,536)
灰粉引兜鉢(Φ12.8xH4.7cm/¥2,376)、灰粉引リム鎬7寸皿(Φ21.5xH3.2cm/¥4,536) 盆栽文八角長皿(W18.2xD11.5xH3cm/¥3,456/稲村真耶)
盆栽文八角長皿(W18.2xD11.5xH3cm/¥3,456/稲村真耶) 白磁輪花楕円鉢(W17.5xD16.5xH5cm/¥3,240/阿部春弥)
白磁輪花楕円鉢(W17.5xD16.5xH5cm/¥3,240/阿部春弥) 白磁鎬矢羽根 4寸甲鉢(Φ12xH4.5cm/¥1,512)、5.5寸甲鉢(Φ16.8xH6.3cm/¥3,456)
白磁鎬矢羽根 4寸甲鉢(Φ12xH4.5cm/¥1,512)、5.5寸甲鉢(Φ16.8xH6.3cm/¥3,456) 同5.5寸甲鉢に白菜とツナの炊いたん。あまりものの手抜き料理ですが美味しいですよ。
同5.5寸甲鉢に白菜とツナの炊いたん。あまりものの手抜き料理ですが美味しいですよ。